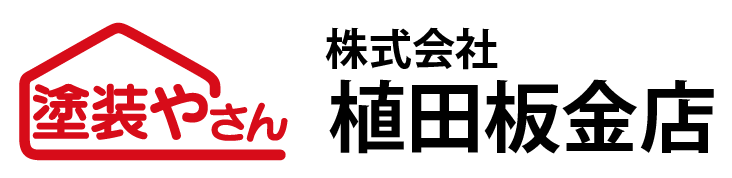外壁塗装を成功させるには下塗りが不可欠!役割や種類を解説

費用を抑えたい方や業者のなかには下塗りを省こうと考える方もいます。
しかし外壁塗装において下塗りは重要な役割をもつ工程なので、省くことはできません。
本記事では外壁塗装における下塗りの重要性や役割について解説します。
外壁塗装を検討している方の参考になる内容なので、ぜひ最後までご覧ください。
外壁塗装で下塗りが重要な理由

しかし下塗りは外壁塗装に欠かせない工程です。
下塗りは塗料の機能面や美観を維持するために重要です。
下塗りの有無によって、外壁塗装全体の仕上がりも変わってきます。
後々不具合が生じて塗り直しが必要になれば、かえって高額な費用がかかる可能性もあります。
外壁塗装における下塗りの役割

・外壁と上塗り塗料を密着させる
・外壁塗料の効果を高める
・塗料が染み込むのを防ぐ
・下地の色を隠して美しく仕上げる
それぞれのポイントを解説します。
外壁と上塗り塗料を密着させる
上塗り塗料と呼ばれる塗料には接着力がほとんどありません。
そのため、上塗り塗料をそのまま外壁に塗ってもすぐ剥がれてしまいます。
下塗り塗料は外壁と上塗り塗料を密着させる役割があります。
下塗りを行うと塗りムラも防げるため、最終的な仕上がりもよくなるというメリットがあります。
そのため、上塗り塗料をそのまま外壁に塗ってもすぐ剥がれてしまいます。
下塗り塗料は外壁と上塗り塗料を密着させる役割があります。
下塗りを行うと塗りムラも防げるため、最終的な仕上がりもよくなるというメリットがあります。
外壁塗装の効果を高める
下塗り塗料には防カビ性・防藻性・防サビ性・遮熱性など、さまざまな機能をもつ製品があります。
基本的に外壁へ機能性をもたせるのは上塗り塗料です。
ただし機能をもつ塗料を選べば、下塗りがその役割を果たすケースもあります。
下塗りは紫外線を反射して外壁を保護するのも役割の一つです。
外壁が受けるダメージを緩和し、耐久性を高める効果も期待できます。
基本的に外壁へ機能性をもたせるのは上塗り塗料です。
ただし機能をもつ塗料を選べば、下塗りがその役割を果たすケースもあります。
下塗りは紫外線を反射して外壁を保護するのも役割の一つです。
外壁が受けるダメージを緩和し、耐久性を高める効果も期待できます。
塗料が染み込むのを防ぐ
外壁には時間の経過によってヒビ割れ・欠けなどが生じます。
表面が荒れていると、そこから塗料が染み込んでしまい塗料の機能性が十分発揮できません。
塗りムラも発生しやすくなります。
下塗りを行って表面を整えると塗料の染み込みや塗りムラを防げます。
表面が荒れていると、そこから塗料が染み込んでしまい塗料の機能性が十分発揮できません。
塗りムラも発生しやすくなります。
下塗りを行って表面を整えると塗料の染み込みや塗りムラを防げます。
下地の色を隠して美しく仕上げる
外壁の色を変える場合、既存の色が透けてしまうと理想通りの色になりません。
特に濃い色から淡い色へと塗り替える場合に起こりやすいケースといえます。
下塗り塗料で既存の外壁の色を覆い隠すと、その後に塗る上塗り塗料の色が綺麗に出てより美しく仕上げられます。
特に濃い色から淡い色へと塗り替える場合に起こりやすいケースといえます。
下塗り塗料で既存の外壁の色を覆い隠すと、その後に塗る上塗り塗料の色が綺麗に出てより美しく仕上げられます。
外壁塗装で下塗りを行わないとどうなる?

・耐久性が低下する
・施工後の仕上がりが悪くなる
・塗料の機能性を発揮しにくくなる
・下地の色がでてきやすくなる
それぞれ順番に見ていきましょう。
耐久性が低下する
外壁塗装での下塗りは塗膜の耐久性を高めます。
下塗りを行わず外壁塗装を実施してしまうと塗膜が剥がれる原因となります。
また下塗りを行わない場合、中塗り・上塗りの塗料が吸い込まれ、ひび割れを起こしてしまうこともあるのです。
塗膜の持ちを良くするためにも下塗りは外壁塗装のなかでも大切な工程となります。
下塗りを行わず外壁塗装を実施してしまうと塗膜が剥がれる原因となります。
また下塗りを行わない場合、中塗り・上塗りの塗料が吸い込まれ、ひび割れを起こしてしまうこともあるのです。
塗膜の持ちを良くするためにも下塗りは外壁塗装のなかでも大切な工程となります。
施工後の仕上がりが悪くなる
下塗りは外壁材と中塗り・上塗りの塗料を密着させる接着剤のような役割を担っています。
下塗りを行わず外壁材のうえに中塗り・上塗りを行ってしまうと塗料の密着性が悪くなってしまい、完成後すぐに剥がれたりひび割れたりします。
仕上がり後の色ムラや艶ムラなどの原因にもなりかねません。
下塗りは外壁塗装後の仕上がりを大きく左右するほど重要な工程でもあるのです。
下塗りを行わず外壁材のうえに中塗り・上塗りを行ってしまうと塗料の密着性が悪くなってしまい、完成後すぐに剥がれたりひび割れたりします。
仕上がり後の色ムラや艶ムラなどの原因にもなりかねません。
下塗りは外壁塗装後の仕上がりを大きく左右するほど重要な工程でもあるのです。
塗料の機能性を発揮しにくくなる
外壁塗装で行う下塗りは、中塗り・上塗りの機能をサポートする役目を果たしています。
下塗りを行わないと中塗り・上塗りの本来の機能性を発揮が難しくなります。
下記のような塗料本来の機能性も発生しにくくなるのは、外壁を塗装する目的を十分に達成できなくなり問題です。
・防カビ機能
・防水機能
・防錆機能
・遮熱機能
・浸透機能
・下地調整機能
塗料によっては上記のような機能性をもったモノがあります。
そのため、塗装を行うことでお家の耐久性が高くなり見栄えが美しく長持ちするのです。
下塗りを行わないと中塗り・上塗りの本来の機能性を発揮が難しくなります。
下記のような塗料本来の機能性も発生しにくくなるのは、外壁を塗装する目的を十分に達成できなくなり問題です。
・防カビ機能
・防水機能
・防錆機能
・遮熱機能
・浸透機能
・下地調整機能
塗料によっては上記のような機能性をもったモノがあります。
そのため、塗装を行うことでお家の耐久性が高くなり見栄えが美しく長持ちするのです。
下地の色がでてきやすくなる
外壁塗装の下塗りは既存の下地の色を隠す役割をもっています。
既存下地の色が濃く使用する塗料が薄い場合、既存下地の色が目立ちやすくなります。
濃い下地色であっても下塗りを行えば、発色のある綺麗な仕上がりが実現可能です。
既存下地の色が濃く使用する塗料が薄い場合、既存下地の色が目立ちやすくなります。
濃い下地色であっても下塗りを行えば、発色のある綺麗な仕上がりが実現可能です。
外壁塗装の下塗り塗料の選び方

専門的な知識が必要になるため業者に任せると安心です。
選ぶ際のポイントは次のような点です。
・外壁の状態に合わせる
・外壁の素材に合わせる
・上塗り塗料との相性を考える
詳しく解説します。
外壁の状態に合わせる
劣化により外壁に生じているヒビ割れ・塗膜の剥がれ・チョーキング(触ると手に粉のようなものが付く状態)などの状態を考慮して必要な下塗り塗料を選びます。
外壁の状態によっては、重ね塗りを行うケースもあります。
外壁の状態によっては、重ね塗りを行うケースもあります。
外壁の素材に合わせる
外壁の素材と相性が悪い下塗り塗料を選んでしまうと密着力が下がり、上塗り塗料が剥がれやすくなってしまいます。
既存の外壁に塗装されている塗料によっては、相性の悪い下塗り塗料が存在します。
不具合が生じる可能性があるため事前の調査が必要です。
既存の外壁に塗装されている塗料によっては、相性の悪い下塗り塗料が存在します。
不具合が生じる可能性があるため事前の調査が必要です。
上塗り塗料との相性を考える
上塗り塗料には水性・弱溶剤型・溶剤型と、さまざまなタイプがあります。
使用する塗料によって、適合する下塗り塗料を選ぶ必要があります。
上塗り塗料を淡い色にするなら下塗り塗料も淡い色を選ぶなど、さまざまな視点からの配慮が必要です。
使用する塗料によって、適合する下塗り塗料を選ぶ必要があります。
上塗り塗料を淡い色にするなら下塗り塗料も淡い色を選ぶなど、さまざまな視点からの配慮が必要です。
外壁塗装における下塗り塗料の種類

・シーラー
・バインダー
・プライマー
・フィラー
・サーフェイサー
・微弾性フィラー
それぞれの性質や特徴を解説します。
シーラー
シーラーは塗料の粘着力を上げる効果をもつ下塗り塗料です。
傷んだ外壁に塗料が吸い込まれるのを防ぐ効果もあるため、劣化が進んでいる場合はシーラーを重ね塗りすると、上塗り塗料を綺麗に密着させられます。
シーラーには水性タイプと油性タイプがあり外壁の状態に合わせて選ばれます。
なおシーラーはコンクリート・モルタル・石膏ボードなどの限られた外壁にしか使用できません。
それ以外の外壁には「浸透性シーラー」と呼ばれる下塗り塗料を選びます。
通常のシーラーでは吸い込まれてしまうような外壁に向いた塗料です。
壁の内部まで届き、外壁自体の強度を高める効果も期待できます。
傷んだ外壁に塗料が吸い込まれるのを防ぐ効果もあるため、劣化が進んでいる場合はシーラーを重ね塗りすると、上塗り塗料を綺麗に密着させられます。
シーラーには水性タイプと油性タイプがあり外壁の状態に合わせて選ばれます。
なおシーラーはコンクリート・モルタル・石膏ボードなどの限られた外壁にしか使用できません。
それ以外の外壁には「浸透性シーラー」と呼ばれる下塗り塗料を選びます。
通常のシーラーでは吸い込まれてしまうような外壁に向いた塗料です。
壁の内部まで届き、外壁自体の強度を高める効果も期待できます。
バインダー
バインダーは劣化の少ない外壁に使用されるタイプの下塗り塗料です。
新築工事で使用されるケースが多くみられます。
塗料を吸い込みにくい外壁の場合も、シーラーよりバインダーを選ぶケースが多くみられます。
新築工事で使用されるケースが多くみられます。
塗料を吸い込みにくい外壁の場合も、シーラーよりバインダーを選ぶケースが多くみられます。
プライマー
プライマーはシーラーと同様に塗料の粘着力を高め、塗料の吸い込みを防ぎます。
メーカーによってはシーラーとプライマーを同じ意味で使っている場合もあります。
プライマーはサビ止め効果をもつものがあるため、鉄・ステンレス・アルミなどの金属下地に使用するのが一般的です。
ただし一般的に防サビ効果はないため、塗装前にしっかりとサビを落とす必要があります。
プライマーのなかには防サビ効果をもつものがあるため確認しておきましょう。
メーカーによってはシーラーとプライマーを同じ意味で使っている場合もあります。
プライマーはサビ止め効果をもつものがあるため、鉄・ステンレス・アルミなどの金属下地に使用するのが一般的です。
ただし一般的に防サビ効果はないため、塗装前にしっかりとサビを落とす必要があります。
プライマーのなかには防サビ効果をもつものがあるため確認しておきましょう。
フィラー
フィラーは凹凸模様の外壁に使用されるケースが多いタイプの下塗り塗料です。
凹凸を平らにならしたり、外壁に発生したヒビ割れを覆ったりする役割があります。
ヒビ割れが起きやすいモルタル壁では、補強効果をもつフィラーが下地塗料に選ばれるケースが多いです。
シーラーやプライマーより厚く塗る必要があります。
粘り気のある材質を活かし、外壁の表面に模様や柄をつけるために厚く塗るケースもあります。
凹凸を平らにならしたり、外壁に発生したヒビ割れを覆ったりする役割があります。
ヒビ割れが起きやすいモルタル壁では、補強効果をもつフィラーが下地塗料に選ばれるケースが多いです。
シーラーやプライマーより厚く塗る必要があります。
粘り気のある材質を活かし、外壁の表面に模様や柄をつけるために厚く塗るケースもあります。
サーフェイサー
サーフェイサーにはシーラーを塗った後の下地の調整や、密着力の向上といった効果があります。
外壁の劣化が進んでいる場合、シーラーと一緒に下塗り塗料として使用されるケースがあります。
外壁の劣化が進んでいる場合、シーラーと一緒に下塗り塗料として使用されるケースがあります。
微弾性フィラー
微弾性フィラーは、シーラーおよびフィラー両方の役割を持つ塗料のことです。
塗膜は柔らかく、伸びる性質を持ちます。
これらの性質があることで建物の動きに追従でき、ひび割れが起きにくい外壁に仕上げることができます。
塗膜は柔らかく、伸びる性質を持ちます。
これらの性質があることで建物の動きに追従でき、ひび割れが起きにくい外壁に仕上げることができます。
外壁塗装で使われる下塗りの色はどんな色?

一般的には以下の下塗り色が使用されることが多いです。
・白色
・灰色
・透明色
・茶色
・黒色
下塗りの色は、使用する塗料の色によって選び方が異なります。
初心者では判断しづらい内容でもあるため、業者に相談しながら色選びを進めましょう。
外壁塗装で下塗りを行う際の成功ポイント

・見積書の内容を確認する
・工程表の項目と日数を確認する
・中塗り塗料と上塗り塗料の色を変える
上記を意識することで手抜き工事業者への依頼を防ぎ、適正な価格での施工依頼につながります。
それぞれ詳しく解説します。
見積書の内容を確認する
工程が書かれている見積書なら、工事内容のなかに下塗りの項目が含まれているか確認しましょう。
数量も「一式」とまとめられて書かれている場合があります。
信頼できる業者は見積書の内容を細かく記載します。
工程ごとの塗装方法、塗料の種類、工事費などが詳しく記載されていると安心です。
大まかな工程しか記載されていない見積書の場合は、業者に内容を詳しく確認しましょう。
塗料名や施工範囲が具体的に記載されているか確認し、記載がない場合は問い合わせておくと確実です。
数量も「一式」とまとめられて書かれている場合があります。
信頼できる業者は見積書の内容を細かく記載します。
工程ごとの塗装方法、塗料の種類、工事費などが詳しく記載されていると安心です。
大まかな工程しか記載されていない見積書の場合は、業者に内容を詳しく確認しましょう。
塗料名や施工範囲が具体的に記載されているか確認し、記載がない場合は問い合わせておくと確実です。
工程表の項目と日数を確認する
外壁塗装において、下塗り・中塗り・上塗りは最短で1日1工程しかできません。
工程表を確認すれば、手抜き工事をしているかどうかある程度は予測できます。
施工範囲や天候によって左右しますが、下塗りから上塗りまで1~2週間ほどかかるのが一般的です。
極端に工期が短い場合は途中の工程を省いている可能性があります。
下塗りに入る前の作業にも要注意です。
外壁は長年の汚れやカビが蓄積しているため、汚れを落とさずに塗装をすると、塗料の耐用年数が落ちる可能性があります。
通常の水洗いでは落としきれない汚れもあるため高圧洗浄が一般的です。
工程表に高圧洗浄が予定されているか確認しましょう。
高圧洗浄後は1~3日の乾燥期間も必要です。
加えて、金属部分にはサビを落とす「ケレン作業」も必要です。
しっかりとサビを落としておくと、塗装の耐久性を高められます。
サイディング外壁はコーキングが劣化している可能性があります。
コーキングが劣化して隙間が生じると雨水が入り込みやすくなり、外壁の劣化につながる可能性もあるため事前に確認してもらいましょう。
工程表を確認すれば、手抜き工事をしているかどうかある程度は予測できます。
施工範囲や天候によって左右しますが、下塗りから上塗りまで1~2週間ほどかかるのが一般的です。
極端に工期が短い場合は途中の工程を省いている可能性があります。
下塗りに入る前の作業にも要注意です。
外壁は長年の汚れやカビが蓄積しているため、汚れを落とさずに塗装をすると、塗料の耐用年数が落ちる可能性があります。
通常の水洗いでは落としきれない汚れもあるため高圧洗浄が一般的です。
工程表に高圧洗浄が予定されているか確認しましょう。
高圧洗浄後は1~3日の乾燥期間も必要です。
加えて、金属部分にはサビを落とす「ケレン作業」も必要です。
しっかりとサビを落としておくと、塗装の耐久性を高められます。
サイディング外壁はコーキングが劣化している可能性があります。
コーキングが劣化して隙間が生じると雨水が入り込みやすくなり、外壁の劣化につながる可能性もあるため事前に確認してもらいましょう。
中塗り塗料の色を変える
下塗り塗料は白色の製品が多いため、中塗り塗料と色を変えてもらうと下塗りを実施したかどうかがわかりやすくなります。
下塗りから上塗りまできちんと塗装してもらったか目に見える形で確認したい場合、中塗り塗料と上塗り塗料の色を変えるという方法もあります。
中塗り塗料と上塗り塗料は、同じ塗料を使うケースが多いです。
しかし同じ色では中塗りの後に上塗りをしたのか、ぱっと見ただけではわかりません。
下塗りから上塗りまで塗料の色が異なれば、一目で今はどの工程なのか確認できます。
塗料は完全に乾いてから重ね塗りを行うため、色が混ざる心配はありません。
下塗りから上塗りまできちんと塗装してもらったか目に見える形で確認したい場合、中塗り塗料と上塗り塗料の色を変えるという方法もあります。
中塗り塗料と上塗り塗料は、同じ塗料を使うケースが多いです。
しかし同じ色では中塗りの後に上塗りをしたのか、ぱっと見ただけではわかりません。
下塗りから上塗りまで塗料の色が異なれば、一目で今はどの工程なのか確認できます。
塗料は完全に乾いてから重ね塗りを行うため、色が混ざる心配はありません。
外壁塗装の下塗り作業前に確認しておきたいこと

・高圧洗浄が行われているか
・下地処理に時間をかけられているか
・安心して依頼できそうな業者か
1つずつ解説していきます。
高圧洗浄が行われているか
高圧洗浄は下塗り前の工程で行われます。
外壁に残る汚れを綺麗にして、外壁への塗料の付着率を高める効果を担っています。
高圧洗浄を行わず外壁塗装を進めてしまうと外壁に塗料が付着しづらくなり、剥がれや剥れなどの原因になってしまいかねません。
最悪の場合、外壁塗装のやり直しになることもあります。
プロの業者であれば問題ないとは思いますが、下塗り前に高圧洗浄が行われているか事前に確認しておくと安心です。
外壁に残る汚れを綺麗にして、外壁への塗料の付着率を高める効果を担っています。
高圧洗浄を行わず外壁塗装を進めてしまうと外壁に塗料が付着しづらくなり、剥がれや剥れなどの原因になってしまいかねません。
最悪の場合、外壁塗装のやり直しになることもあります。
プロの業者であれば問題ないとは思いますが、下塗り前に高圧洗浄が行われているか事前に確認しておくと安心です。
下地処理に時間がかけられているか
下地処理がしっかり行われていると塗料の付着率が高まります。
下地処理が行われているかどうかに、ケレン作業が実施されているかが挙げられます。
コーキングの補修も下地処理に欠かせないため、それぞれの補修工事と作業の内容を工事前に確認し、時間がかけられていることを確認しておきましょう。
下地処理が行われているかどうかに、ケレン作業が実施されているかが挙げられます。
コーキングの補修も下地処理に欠かせないため、それぞれの補修工事と作業の内容を工事前に確認し、時間がかけられていることを確認しておきましょう。
安心して依頼できそうな業者か
工程に沿って進められていたとしても業者選びに失敗すると、手抜き工事や高額費用の請求トラブルの原因になります。
トラブルを未然に回避するためにも、安心して信頼できそうな業者を選ぶ必要があります。
トラブルを未然に回避するためにも、安心して信頼できそうな業者を選ぶ必要があります。
外壁塗装を任せられる業者を探すときのコツ

・実績が豊富にあるか
・資格を所有している職人が在籍しているか
・メディアへの掲載実績があるか
・問い合わせの時の業者の対応に違和感はないか
これから外壁塗装を検討している方は、3つのコツを参考にしてみてください。
実績が豊富にあるか
実績が豊富にあることで仕上がりや施工実績などを事前に確認できます。
事前に確認できることで、実際に外壁塗装を実施してもらう際の仕上がりもイメージできます。
実績はホームページで確認可能です。
塗装やさん(運営:植田板金店)では年間施工実績3,000棟以上を誇っていますので、業者選びの参考にしてみてください。
事前に確認できることで、実際に外壁塗装を実施してもらう際の仕上がりもイメージできます。
実績はホームページで確認可能です。
塗装やさん(運営:植田板金店)では年間施工実績3,000棟以上を誇っていますので、業者選びの参考にしてみてください。
資格を所有している職人が在籍しているか
外壁塗装を任せられる業者を選ぶ際、建築士や建築板金技能士など、外壁工事に関わる資格を持つ職人が在籍しているかチェックしましょう。
資格を所有している職人は、技術力・知識力ともに高いことが期待できるため、安心して任せられます。
資格を所有している職人が在籍しているかどうかは、ホームページでチェックできることが多いです。
塗装やさん(運営:植田板金店)では、一級建築士や一級建築板金技能士などを所有している職人が多数在籍しています。
高い技術力・知識力を兼ね揃えている職人が多数在籍しているので、安心してお任せください。
資格を所有している職人は、技術力・知識力ともに高いことが期待できるため、安心して任せられます。
資格を所有している職人が在籍しているかどうかは、ホームページでチェックできることが多いです。
塗装やさん(運営:植田板金店)では、一級建築士や一級建築板金技能士などを所有している職人が多数在籍しています。
高い技術力・知識力を兼ね揃えている職人が多数在籍しているので、安心してお任せください。
メディアへの掲載実績があるか
メディアへの掲載実績があるかどうかも、業者を探すときのコツになります。
メディアへ掲載されているということは、それだけ第三者からも信頼を獲得できている業者であることの証になります。
もちろん「メディアに取り上げられた業者=優良」とは限りませんが、業者を選ぶときの基準の1つにはなるでしょう。
塗装やさん(運営:植田板金店)では、数多くのメディアへの掲載実績があります。
たとえば、日本テレビ「ヒルナンデス」やRNC西日本放送など、全国各地で放送されているテレビに出演しています。
また、岡山県を中心にテレビだけでなく、新聞や雑誌、ラジオなどへの掲載実績も豊富です。
塗装やさん(運営:植田板金店)のメディアへの掲載実績について気になる方は、こちらをご確認ください。
メディアへ掲載されているということは、それだけ第三者からも信頼を獲得できている業者であることの証になります。
もちろん「メディアに取り上げられた業者=優良」とは限りませんが、業者を選ぶときの基準の1つにはなるでしょう。
塗装やさん(運営:植田板金店)では、数多くのメディアへの掲載実績があります。
たとえば、日本テレビ「ヒルナンデス」やRNC西日本放送など、全国各地で放送されているテレビに出演しています。
また、岡山県を中心にテレビだけでなく、新聞や雑誌、ラジオなどへの掲載実績も豊富です。
塗装やさん(運営:植田板金店)のメディアへの掲載実績について気になる方は、こちらをご確認ください。
問い合わせ時の業者の対応に違和感はないか
外壁塗装を任せられる業者を選ぶ際、問い合わせ時の対応に違和感がないかも確認しておきましょう。
外壁塗装をはじめとしたお家のリフォームは、金額の大小だけでは決められません。
担当者や会社の対応がいいか、業者の対応に違和感を覚えることはないかなどを見極められず、依頼してしまうと、思ったように工事を進めてもらうことが難しくなります。
お互いにストレスを溜めてしまう原因にもなるため、まずは問い合わせ時の業者に違和感はないかを確認しましょう。
塗装やさん(運営:植田板金店)では、社員教育を徹底しております。
気持ちの良いお客様対応には自信がありますので、気になった方はお問い合わせフォームからご連絡ください。
外壁塗装をはじめとしたお家のリフォームは、金額の大小だけでは決められません。
担当者や会社の対応がいいか、業者の対応に違和感を覚えることはないかなどを見極められず、依頼してしまうと、思ったように工事を進めてもらうことが難しくなります。
お互いにストレスを溜めてしまう原因にもなるため、まずは問い合わせ時の業者に違和感はないかを確認しましょう。
塗装やさん(運営:植田板金店)では、社員教育を徹底しております。
気持ちの良いお客様対応には自信がありますので、気になった方はお問い合わせフォームからご連絡ください。
外壁塗装は下塗りから丁寧に行うことが重要

専門業者に外壁の状態を調査してもらい、適切な塗料を選んでもらいましょう。
悪徳業者に依頼すると、高額な費用を請求される恐れがあります。
見積書の内容を確認し、詳細な項目まで明示している信頼感のある業者を選ぶと安心です。
▼関連記事
外壁塗装の工程や日数を解説!生活時に注意すべきポイントも紹介