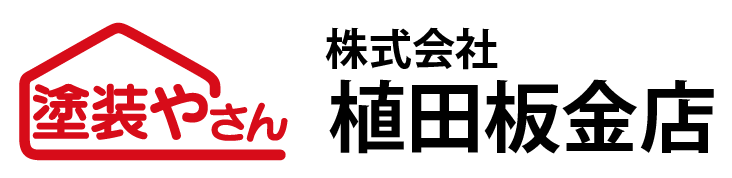屋根塗装の全工程をステップごとに解説!施工にかかる日数も紹介

「施工が完了するまでにどれくらいの日数がかかるの?」
屋根塗装の施工を検討している方にとって「塗装の全工程」や「施工にかかる日数」は気になるポイントです。
屋根塗装は正しい工程で施工されることで、高品質な仕上がりになります。
一方で手抜き工事によって必要な工程が省略されてしまうと、たとえ高性能な塗料を使用していても低品質な仕上がりになってしまいかねません。
本記事では「屋根塗装の工程」と「全工程にかかる日数」を解説します。
屋根は素材によって工程が異なるため、素材別の工程も紹介します。
また、屋根塗装を行ううえで知っておきたいポイントも解説するので、施工全体への理解が深まるでしょう。
手抜き工事がないか見極めるための判断材料にもなるので、ぜひ参考にしてみてください。
屋根塗装の工程

・近隣住民へのあいさつ
・事前準備
・足場組立
・高圧洗浄
・下地処理
・養生
・下塗り
・タスペーサーの挿入
・中塗り
・上塗り
・完了検査
・足場撤去
・施工完了(引き渡し)
それぞれの工程について、詳しく解説していきます。
近隣住民へのあいさつ
塗装工事が始まると騒音や振動、塗料の臭いなどで近隣住民の生活に影響を与えてしまう可能性があります。
ご近所トラブルを避けるためにも、近隣住民へ事前にあいさつをしておくことが大切です。
作業内容や施工期間を丁寧に説明しておけば、近隣住民も安心できるのでトラブルに発展する可能性は低くなります。
あいさつは施工業者のスタッフが行ってくれることが多い印象です。
ただし今後の近所付き合いを考えると、業者に任せきりにせず施主も一緒にあいさつすることがおすすめです。
ご近所トラブルを避けるためにも、近隣住民へ事前にあいさつをしておくことが大切です。
作業内容や施工期間を丁寧に説明しておけば、近隣住民も安心できるのでトラブルに発展する可能性は低くなります。
あいさつは施工業者のスタッフが行ってくれることが多い印象です。
ただし今後の近所付き合いを考えると、業者に任せきりにせず施主も一緒にあいさつすることがおすすめです。
事前準備
施工が始まる前に、作業の邪魔になりそうな物を移動しておく必要があります。
業者が勝手に物を移動させるとトラブルの原因になるので、施主が立ち会いのもとで行います。
「大切に扱ってほしいもの」や「汚されたくないもの」があれば、事前に伝えておきましょう。
業者が勝手に物を移動させるとトラブルの原因になるので、施主が立ち会いのもとで行います。
「大切に扱ってほしいもの」や「汚されたくないもの」があれば、事前に伝えておきましょう。
足場組立
安全に塗装作業をするために、仮設足場を設置します。
後の工程で家全体を養生する必要があるため、周囲を囲う形で足場を設置していきます。
屋根の勾配が急な場合には、作業の安全性を確保するため屋根の上にも足場設置が必要です。
足場組立の際には騒音が発生してしまうため「どの程度の音がするか」「作業する時間帯はいつか」などを事前に確認しておきましょう。
後の工程で家全体を養生する必要があるため、周囲を囲う形で足場を設置していきます。
屋根の勾配が急な場合には、作業の安全性を確保するため屋根の上にも足場設置が必要です。
足場組立の際には騒音が発生してしまうため「どの程度の音がするか」「作業する時間帯はいつか」などを事前に確認しておきましょう。
高圧洗浄
高圧洗浄機を使用して、屋根に付着している汚れを洗い流します。
【高圧洗浄で洗い流すもの】
・汚れ、ほこり
・カビ、コケ
・剥がれかけている古い塗料
洗浄が不十分だと塗料の付きが均一になりにくく、施工後に塗装が剥がれてしまうかもしれません。
屋根塗装を高品質な仕上がりにするために、念入りに洗浄を実施します。
【高圧洗浄で洗い流すもの】
・汚れ、ほこり
・カビ、コケ
・剥がれかけている古い塗料
洗浄が不十分だと塗料の付きが均一になりにくく、施工後に塗装が剥がれてしまうかもしれません。
屋根塗装を高品質な仕上がりにするために、念入りに洗浄を実施します。
下地処理
塗装前の準備として、下地処理を行います。
下地処理でおこなう作業は以下の通りです。
・釘打ち
・ひび割れ補修
・金属部分の研磨
それぞれの内容は以下のとおりです。
【釘打ち】
屋根の頂上にある「棟板金」といわれる部材を固定している釘が抜けていないか点検します。
釘が抜けているところがあれば打ち直しが必要です。
【ひび割れ補修】
屋根のひび割れをコーキングで補修します。
コーキングとはひび割れや隙間を埋める樹脂製の充填剤のことです。
【金属部分の研磨】
金属部分のサビや汚れを落とすためにブラシやヤスリなどで研磨を行います。
作業後は研磨により発生した削りカスを丁寧に掃除することが大切です。
削りカスが付着したままだと、塗装の際に塗料の密着性が低くなってしまうため注意しましょう。
下地の処理が不十分だと、塗装した塗料が剥がれやすくなり施工後の耐久性に悪影響を与えかねません。
下地処理は、仕上がりに大きく影響する重要な工程だと理解しておきましょう。
下地処理でおこなう作業は以下の通りです。
・釘打ち
・ひび割れ補修
・金属部分の研磨
それぞれの内容は以下のとおりです。
【釘打ち】
屋根の頂上にある「棟板金」といわれる部材を固定している釘が抜けていないか点検します。
釘が抜けているところがあれば打ち直しが必要です。
【ひび割れ補修】
屋根のひび割れをコーキングで補修します。
コーキングとはひび割れや隙間を埋める樹脂製の充填剤のことです。
【金属部分の研磨】
金属部分のサビや汚れを落とすためにブラシやヤスリなどで研磨を行います。
作業後は研磨により発生した削りカスを丁寧に掃除することが大切です。
削りカスが付着したままだと、塗装の際に塗料の密着性が低くなってしまうため注意しましょう。
下地の処理が不十分だと、塗装した塗料が剥がれやすくなり施工後の耐久性に悪影響を与えかねません。
下地処理は、仕上がりに大きく影響する重要な工程だと理解しておきましょう。
養生
塗装を行う際は、塗料が周囲に飛散する場合があります。
塗装する面以外への塗料の付着を避けるため、マスキングテープや養生用のビニールシートを活用します。
塗料などが近隣に飛散しないように、家の周囲にも飛散防止用のネットで養生を行うなど、優良業者であれば適切な対応を実施してくれるものです。
塗装する面以外への塗料の付着を避けるため、マスキングテープや養生用のビニールシートを活用します。
塗料などが近隣に飛散しないように、家の周囲にも飛散防止用のネットで養生を行うなど、優良業者であれば適切な対応を実施してくれるものです。
下塗り
屋根を塗装していく工程では「下塗り」「中塗り」「上塗り」と、塗料を3回塗り重ねることが基本です。
下塗りは、屋根材と塗料の密着性を高めることを目的としています。
下塗り塗料にはさまざまな種類があり、屋根の状態や材質に応じて適切な塗料を選定します。
施工業者の方針や使用する塗料によっては塗り重ねの回数が異なるため、事前に確認しておきましょう。
下塗りは、屋根材と塗料の密着性を高めることを目的としています。
下塗り塗料にはさまざまな種類があり、屋根の状態や材質に応じて適切な塗料を選定します。
施工業者の方針や使用する塗料によっては塗り重ねの回数が異なるため、事前に確認しておきましょう。
タスペーサーの挿入
ご自宅の屋根がスレート屋根を使用している場合、タスペーサーという部材の挿入が必要です。
塗装によって屋根材が重なる部分に塗料が入り込んでしまうと、隙間が埋まってしまい雨水が流れにくくなります。
内部に雨水が溜まることで腐食が発生して、雨漏りの原因になりかねません。
対策としてタスペーサーを挿入することで、屋根材が重なる部分の隙間を確保します。
塗装後に塞がった隙間をカッターで取り除く「縁切り」という方法もありますが、以下のデメリットがあるため現在ではあまり行われていません。
【カッターで縁切りを行うデメリット】
・屋根を傷つけてしまう可能性がある
・作業に手間と時間がかかる
・施工費用が高くなる
ただし屋根の形状や種類によってタスペーサーが使用できない場合には、縁切りを行うケースもあります。
「縁切りを行うか」「タスペーサーを使用するか」の2点を施工業者に確認しておきましょう。
塗装によって屋根材が重なる部分に塗料が入り込んでしまうと、隙間が埋まってしまい雨水が流れにくくなります。
内部に雨水が溜まることで腐食が発生して、雨漏りの原因になりかねません。
対策としてタスペーサーを挿入することで、屋根材が重なる部分の隙間を確保します。
塗装後に塞がった隙間をカッターで取り除く「縁切り」という方法もありますが、以下のデメリットがあるため現在ではあまり行われていません。
【カッターで縁切りを行うデメリット】
・屋根を傷つけてしまう可能性がある
・作業に手間と時間がかかる
・施工費用が高くなる
ただし屋根の形状や種類によってタスペーサーが使用できない場合には、縁切りを行うケースもあります。
「縁切りを行うか」「タスペーサーを使用するか」の2点を施工業者に確認しておきましょう。
中塗り
外壁をムラなく均一に塗装するためには、中塗りの工程が重要です。
中塗りをせずに上塗り1回だけの施工だと、仕上がりにムラが出てしまいます。
中塗りは手抜き工事で省かれる可能性があるため、事前に工程表を確認することが大切です。
手抜き工事がないか見極めるために「塗料の乾燥時間」や「施工期間が極端に短くないか」というポイントに注目しましょう。
中塗りをせずに上塗り1回だけの施工だと、仕上がりにムラが出てしまいます。
中塗りは手抜き工事で省かれる可能性があるため、事前に工程表を確認することが大切です。
手抜き工事がないか見極めるために「塗料の乾燥時間」や「施工期間が極端に短くないか」というポイントに注目しましょう。
上塗り
中塗り後に塗料をしっかり乾燥させてから、仕上げの上塗りを施工していきます。
上塗りの目的は「中塗りの際に残ったムラを平滑にすること」と「塗膜に厚みを持たせること」です。
上塗りを丁寧に施工できれば、美観と耐久性を兼ね備えた仕上がりになります。
上塗りの目的は「中塗りの際に残ったムラを平滑にすること」と「塗膜に厚みを持たせること」です。
上塗りを丁寧に施工できれば、美観と耐久性を兼ね備えた仕上がりになります。
完了検査
塗装が完了したら、完了検査を実施します。
【完了検査の項目】
・全体の仕上がり
・塗り残しの有無
・周囲への飛散の有無
施主は屋根の上には登れないため、窓やベランダなどから視認できる範囲で確認します。
自分の目で徹底的に確認したい場合は、業者に写真や動画を撮影してもらえるか聞いてみましょう。
完了検査をしている中で少しでも気になることがあれば、質問することも大切です。
塗装やさんでは経験豊富なスタッフが細部まで点検し、問題があれば即時に対応します。
【完了検査の項目】
・全体の仕上がり
・塗り残しの有無
・周囲への飛散の有無
施主は屋根の上には登れないため、窓やベランダなどから視認できる範囲で確認します。
自分の目で徹底的に確認したい場合は、業者に写真や動画を撮影してもらえるか聞いてみましょう。
完了検査をしている中で少しでも気になることがあれば、質問することも大切です。
塗装やさんでは経験豊富なスタッフが細部まで点検し、問題があれば即時に対応します。
足場撤去
検査にて問題がなければ、足場を撤去していきます。
足場組立と同様に足場撤去の際にも騒音が発生するため、作業する時間帯を確認しておきましょう。
足場組立と同様に足場撤去の際にも騒音が発生するため、作業する時間帯を確認しておきましょう。
施工完了(引き渡し)
塗装業者の片づけが終われば、施工完了となります。
保証書が発行されたら、内容をしっかりと確認しておきましょう。
工程に沿って適切に作業を進めることで、安全かつ確実に塗装工事が実施できます。
保証書が発行されたら、内容をしっかりと確認しておきましょう。
工程に沿って適切に作業を進めることで、安全かつ確実に塗装工事が実施できます。
【屋根の素材別】塗装の工程

次の素材別に、それぞれの工程を紹介します。
・スレート屋根
・ガルバリウム鋼板屋根
・モニエル瓦屋根
・トタン屋根
・折板屋根
なお、塗料を塗る回数は使用する製品によっても異なります。
必要な塗装回数は、製品の説明書や販売元のホームページなどで確認できます。
スレート屋根
スレートとは粘土板岩を用いた薄い板状の屋根材で「カラーベスト」「コロニアル」とも呼ばれます。
スレート屋根を塗装する場合の主な工程は、次の通りです。
・高圧洗浄
・縁切り
・下塗り
・中塗り
・上塗り
高圧洗浄で屋根に付着したコケや藻、カビといった汚れをしっかり落とします。
汚れが残っていると塗り直してもすぐ剥がれてしまうため、丁寧な洗浄が必要です。
また、スレート瓦とスレート瓦の間に隙間を作るために、縁切りは必須の工程です。
スレート屋根を塗装する場合の主な工程は、次の通りです。
・高圧洗浄
・縁切り
・下塗り
・中塗り
・上塗り
高圧洗浄で屋根に付着したコケや藻、カビといった汚れをしっかり落とします。
汚れが残っていると塗り直してもすぐ剥がれてしまうため、丁寧な洗浄が必要です。
また、スレート瓦とスレート瓦の間に隙間を作るために、縁切りは必須の工程です。
ガルバリウム鋼板
ガルバリウム鋼板とは、アルミニウム・亜鉛合金めっき鋼板で、トタン屋根よりさびにくく耐久性が高いのが特徴です。
ガルバリウム鋼板屋根を塗装する場合の主な工程は、次の通りです。
・ケレン
・下塗り
・中塗り
・上塗り
ケレンとは、屋根材の研磨を行う下地処理のことです。
屋根材の表面を粗くすると同時に、劣化して剥がれかけている古い塗膜も削り取ります。
塗料と下地の密着性が高まり、剥がれにくくなります。
ガルバリウム鋼板屋根を塗装する場合の主な工程は、次の通りです。
・ケレン
・下塗り
・中塗り
・上塗り
ケレンとは、屋根材の研磨を行う下地処理のことです。
屋根材の表面を粗くすると同時に、劣化して剥がれかけている古い塗膜も削り取ります。
塗料と下地の密着性が高まり、剥がれにくくなります。
モニエル瓦屋根
モニエル瓦は「乾式洋瓦」とも呼ばれます。
モニエル瓦屋根を塗装する場合、主な工程は次の通りです。
・高圧洗浄
・下塗り
・中塗り
・上塗り
モニエル瓦屋根の場合、高圧洗浄が重要です。
モニエル瓦にはスラリー層と呼ばれる部分があり、塗装する前に取り除く必要があるからです。
スラリー層が残ったままでは、新しく塗った塗料が剥がれやすくなってしまいます。
コケや藻といった汚れとともに、しっかりとスラリー層を除去してから塗装を行います。
モニエル瓦屋根を塗装する場合、主な工程は次の通りです。
・高圧洗浄
・下塗り
・中塗り
・上塗り
モニエル瓦屋根の場合、高圧洗浄が重要です。
モニエル瓦にはスラリー層と呼ばれる部分があり、塗装する前に取り除く必要があるからです。
スラリー層が残ったままでは、新しく塗った塗料が剥がれやすくなってしまいます。
コケや藻といった汚れとともに、しっかりとスラリー層を除去してから塗装を行います。
トタン屋根
トタン屋根とは、アルミニウム・亜鉛めっき鋼板などを使用した屋根です。
トタン屋根を塗装する場合、主な工程は次の通りです。
・ケレン
・下塗り
・中塗り
・上塗り
ケレンとは、屋根の下地処理です。
劣化した塗料や汚れを削り取るだけでなく、新たな塗料と下地の密着力を高めるために屋根材の表面の目を粗くします。
塗装の仕上がりを左右する重要な工程です。
また、トタン屋根はサビが発生しやすいため、サビ止め効果をもつ塗料の使用がおすすめです。
トタン屋根を塗装する場合、主な工程は次の通りです。
・ケレン
・下塗り
・中塗り
・上塗り
ケレンとは、屋根の下地処理です。
劣化した塗料や汚れを削り取るだけでなく、新たな塗料と下地の密着力を高めるために屋根材の表面の目を粗くします。
塗装の仕上がりを左右する重要な工程です。
また、トタン屋根はサビが発生しやすいため、サビ止め効果をもつ塗料の使用がおすすめです。
折板屋根
折板屋根は、波型の形をした屋根を指します。
鋼板を波型にすることで強度を高めています。
折板屋根を塗装する場合、主な工程は次の通りです。
・高圧洗浄
・ケレン
・下塗り
・中塗り
・上塗り
折板屋根のサビは高圧洗浄では落とせないため、ケレンの工程でしっかりと削り落とします。
また、折板屋根はさびやすいため、サビ止め効果のある塗料の使用がおすすめです。
鋼板を波型にすることで強度を高めています。
折板屋根を塗装する場合、主な工程は次の通りです。
・高圧洗浄
・ケレン
・下塗り
・中塗り
・上塗り
折板屋根のサビは高圧洗浄では落とせないため、ケレンの工程でしっかりと削り落とします。
また、折板屋根はさびやすいため、サビ止め効果のある塗料の使用がおすすめです。
屋根塗装の全工程にかかる日数

屋根とあわせて外壁塗装も実施する場合、目安の日数は10〜14日です。
屋根の面積や劣化具合によって、施工期間は前後します。
天候により塗装をできない日が発生すると、施工期間が延びる場合もあります。
日数はあくまで目安のため、条件や環境によって前後することを覚えておきましょう。
屋根塗装の工程を確認する方法

より具体的にスケジュールを把握したい場合は「工事工程表」を確認しましょう。
「工事工程表」は多くの塗装業者が着工前に作成するもので、具体的な塗装のスケジュールがわかるようになっています。
ただし、工事工程表に書かれているのはあくまで予定です。
天候や、実際に工事を始めてからわかった不具合などで、屋根塗装のスケジュールは前後すると考えてください。
工程表のスケジュールに変更が生じた場合、連絡してくれるようお願いしておくと最新の情報を教えてもらえます。
また、工程表を確認すると、下地処理をしていない、中塗りを省かれているといった手抜き工事を防ぐ効果も期待できます。
屋根塗装について知っておきたいこと

事前に知っておくと安心できる内容を紹介します。
・塗装中は窓を開けられないタイミングがある
・塗料の臭いが気になる可能性がある
・塗装中は洗濯物を屋外に干せない
・塗装中は基本的に留守でも問題ない
それぞれ解説します。
塗装中は窓を開けられないタイミングがある
塗装工事中、高圧洗浄を行っているタイミングでは窓を開けられません。
一方、下塗り・中塗り・上塗りの段階では、窓を開けられる場合もあります。
しかし、塗料の匂いが室内に入る可能性があるため、窓は閉めておく方が無難です。
また、塗装方法によっては窓を開けられない場合もあります。
エアコンや換気扇は使用できるため、室温の調整は窓の開閉以外で行いましょう。
ただし、エアコンの室外機を養生する場合もあるため、使用する場合は業者に伝えておきましょう。
一方、下塗り・中塗り・上塗りの段階では、窓を開けられる場合もあります。
しかし、塗料の匂いが室内に入る可能性があるため、窓は閉めておく方が無難です。
また、塗装方法によっては窓を開けられない場合もあります。
エアコンや換気扇は使用できるため、室温の調整は窓の開閉以外で行いましょう。
ただし、エアコンの室外機を養生する場合もあるため、使用する場合は業者に伝えておきましょう。
塗料の臭いが気になる可能性がある
屋根は室内から距離があるため、塗料の臭いが気にならない方もいます。
しかし「塗料の臭いが非常に気になる」と感じる方も少なくありません。
臭いに敏感な方は、下塗りから上塗りの工程中は窓やドアを開けないようにするとよいでしょう。
できるだけ家にいないようにする、塗料選びの際に臭いにも配慮する、といった方法も有効です。
なお、塗料の臭いが原因で近隣からクレームを受けるケースもあり、事前のあいさつが大切になります。
しかし「塗料の臭いが非常に気になる」と感じる方も少なくありません。
臭いに敏感な方は、下塗りから上塗りの工程中は窓やドアを開けないようにするとよいでしょう。
できるだけ家にいないようにする、塗料選びの際に臭いにも配慮する、といった方法も有効です。
なお、塗料の臭いが原因で近隣からクレームを受けるケースもあり、事前のあいさつが大切になります。
塗装中は洗濯物を屋外に干せない
屋根の塗装工事中は基本的に洗濯物を屋外に干せないため、対応を考えておきましょう。
高圧洗浄を行う際の水や塗料などで洗濯物が汚れてしまったり、塗料の臭いがついたりする可能性もあります。
対応としては、室内干しやコインランドリー、洗濯機や浴室の乾燥機能の利用が挙げられます。
洗濯物を干せるタイミングについては、業者に確認すると確実です。
高圧洗浄を行う際の水や塗料などで洗濯物が汚れてしまったり、塗料の臭いがついたりする可能性もあります。
対応としては、室内干しやコインランドリー、洗濯機や浴室の乾燥機能の利用が挙げられます。
洗濯物を干せるタイミングについては、業者に確認すると確実です。
塗装中は基本的に留守でも問題ない
屋根の塗装工事は屋外で行うため、留守宅でも進行できます。
しかし、以下のタイミングは施主の立ち会いが求められるため、誰かが在宅する必要があります。
・事前準備(現場確認)
・完了検査
施主が不在のときは電話などで報告してくれる業者もいるため、状況を把握したい方は相談してみましょう。
しかし、以下のタイミングは施主の立ち会いが求められるため、誰かが在宅する必要があります。
・事前準備(現場確認)
・完了検査
施主が不在のときは電話などで報告してくれる業者もいるため、状況を把握したい方は相談してみましょう。
屋根塗装で重要なポイント

・事前に点検や調査をしているか
・詳細な見積書を出してくれるか
・業者のアフターフォローは十分か
それぞれの内容を把握し、トラブルに巻き込まれないように注意しましょう。
事前に点検や調査をしているか
屋根の状態を正確に把握しなければ、適切な見積もりは出せません。
見積もりを出してもらう前に、丁寧な事前点検を行う必要があります。
直接屋根に登るか、ドローンなどを使うかして、実際の屋根の状態を確認してもらいましょう。
屋根の状態によって、選ぶ塗料が変わったり、塗装前に補修が必要になったりします。
事前点検をしないと、工事が始まってから追加費用が発生する、補修が必要だったが無視される、といったリスクがあります。
費用はかかりますが、適切な施工のために必要だと考えましょう。
見積もりを出してもらう前に、丁寧な事前点検を行う必要があります。
直接屋根に登るか、ドローンなどを使うかして、実際の屋根の状態を確認してもらいましょう。
屋根の状態によって、選ぶ塗料が変わったり、塗装前に補修が必要になったりします。
事前点検をしないと、工事が始まってから追加費用が発生する、補修が必要だったが無視される、といったリスクがあります。
費用はかかりますが、適切な施工のために必要だと考えましょう。
詳細な見積書を出してくれるか
塗装を依頼する業者は、見積書を出してくれるところを選びましょう。
口約束だけでは、後からトラブルの原因になります。
必ず書面で詳細を残しておきましょう。
また「一式」などざっくりとした見積もりを出す業者にも注意が必要です。
詳細が記載されていないと「その工賃は見積もりに含まれていない」と、トラブルに発展するリスクがあります。
使用する材料や塗料の種類、塗る範囲などが記載されていると信頼できる見積書といえます。
安心して任せられる業者を選びましょう。
口約束だけでは、後からトラブルの原因になります。
必ず書面で詳細を残しておきましょう。
また「一式」などざっくりとした見積もりを出す業者にも注意が必要です。
詳細が記載されていないと「その工賃は見積もりに含まれていない」と、トラブルに発展するリスクがあります。
使用する材料や塗料の種類、塗る範囲などが記載されていると信頼できる見積書といえます。
安心して任せられる業者を選びましょう。
業者のアフターフォローは十分か
屋根の塗装工事が終わった直後は問題なかったとしても、時間が経って問題が発生するケースがあります。
業者のアフターフォローがしっかりしていれば、問題が発生しても安心です。
保証期間内は責任をもって対応してくれます。
あらかじめアフターフォローの内容、保証期間を確認しておきましょう。
業者のアフターフォローがしっかりしていれば、問題が発生しても安心です。
保証期間内は責任をもって対応してくれます。
あらかじめアフターフォローの内容、保証期間を確認しておきましょう。
屋根塗装の工程を理解して施工を依頼しよう

本記事では、屋根塗装の工程と施工にかかる日数を詳しく解説しました。
屋根塗装の工程と日数を理解できれば、施工時に余計な不安やストレスを溜めることなくスムーズに対応できます。
工程を理解すると手抜き工事を実施するような悪徳業者も見極めやすくなります。
本記事を参考にして、信頼できる業者に外壁塗装の施工を依頼しましょう。
▼関連記事
外壁塗装と屋根塗装は同時の施工がおすすめ!理由と注意点を紹介
屋根の縁切りはなぜ必要?縁切りが不要なケース・やり方を解説
屋根塗装は足場なしで安全にできる?必要な理由や違法性を解説